ヘッダーの絵を題材にめざしている全体像を述べたいと思います。ヘッダの全体の絵はこれです。このブログではプログラムについて多く述べるつもりでいます。私はTouchDesigner, MAX, blenderを使っています。初めて投稿したVaring durationという曲はMAXで作製したものです。この絵はTouchDesignerとblenderを利用して描いたものです。詳細は後日述べていきたいと思っています。絵自体も背景が文字を見にくくしているので、色を変更したいと思っております。近いうちに修正しようと思っています。そうしたことより、ここではヘッダーの部分で述べた、分析・解析と違う次元、どう役立つかとは違う次元として、この絵を題材にして述べようと思います。次元といっているのは、直交するベクトルのことです。私は分析・解析や、どう役立つかと言ったベクトルと違う方向に興味を持っているということです。小林英雄は講演で自分は歴史が好きで、歴史を学ぶことは自分を知ることになる、と話しています。これは、織田信長や明智光秀に興味を持ったとすると、そこには何がしら彼らの中に共感することや、反対することを感じるからである。つまり私ってそういうところがあるということを知ることになるというわけです。こうしたことは何からでも得られますが、歴史は登場人物が大変多いので、自分の多くの側面を探せるというわけです。好きな絵や音楽も似たようなところがあります。自分はこういう感じが好きなんだ、というこうがわかってきます。どうやら私は何かが隠されている、と感じれるモノが好きなようです。朽ちた三柱の御柱、何か意味がありそうじゃないですか、こうして勝手にイメージを膨らませ、それぞれの物語を見出すことをナラティブといいます。私はモノに接した時に、ナラティブを思えるようなモノってどんなモノだろう、ということに興味を持っています。それぞれの柱には部族の印しとしての文様が描いてあります。今では失われた部族で朽ちた御柱であるので、意味がわからないような文様でいいわけです。そのために意味不明な文様を作る必要がありました。私は文様にも興味があり次々と文様を作り出すプログラムを作製しております(TouchDesignerによる)。このプログラムを利用して文様を作製しました。文様が少々浮き出ているようにするために、ディスプレイスメントという技術を使っております。この技術を知った時は感激しました。色を凹凸に変換する技術です(色はプログラムでは、このうように凸凹つまり3D形状に変換する技術のほかに、3次元座標に当てはめることもよく行います。これでベクトル演算が行えるのです。これも驚嘆する技術です)。こうした技術もおいおい紹介していきたいと思います。また御柱はぼこぼこと、ところどころへこんでいます。これもディスプレイスメントです(柱を凸凹にして朽ちたようにするのにblenderを使っています)。森の中に部族の文様が描いてある朽ちた御柱が立っている。そこに隠された意味を感じるというのが、モノがあるから感じれる別の次元だというわけです。私はインタラクションに関心があり、これは体験を作るモノです。絵では身体を伴う体験は難しいですが、インターラクションができないわけではありません。例えば上述のようなことを思ったということは、絵を描く前と気持ちが変わったということです。この変わった気持ちでもう一度見ると、また自分の作るナラティブも変化するわけです。これを連続していくわけです。このようなことがモノと私との間で起こるフィードバックです。如何にモノと私との間でフィードバックを作るのか、これがインターラクションの面白さであり、探求するところです。家ではなかなかインターラクションする装置は作れませんが、それを感じ取れるプログラムを中心としたモノを作っていきたいと思っております。こうしたモノとの間にフィードバックが成立すると、私と利用するモノ、という関係を超え、モノと私とは関係性を作っていくことになります。これは言葉ではなかなか表現しにくい体験となります。今日はヘッダーの絵を題材に、バクっとした主張点を述べてみました。
バクっとした主張点
 ナラティブ
ナラティブ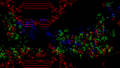

コメント